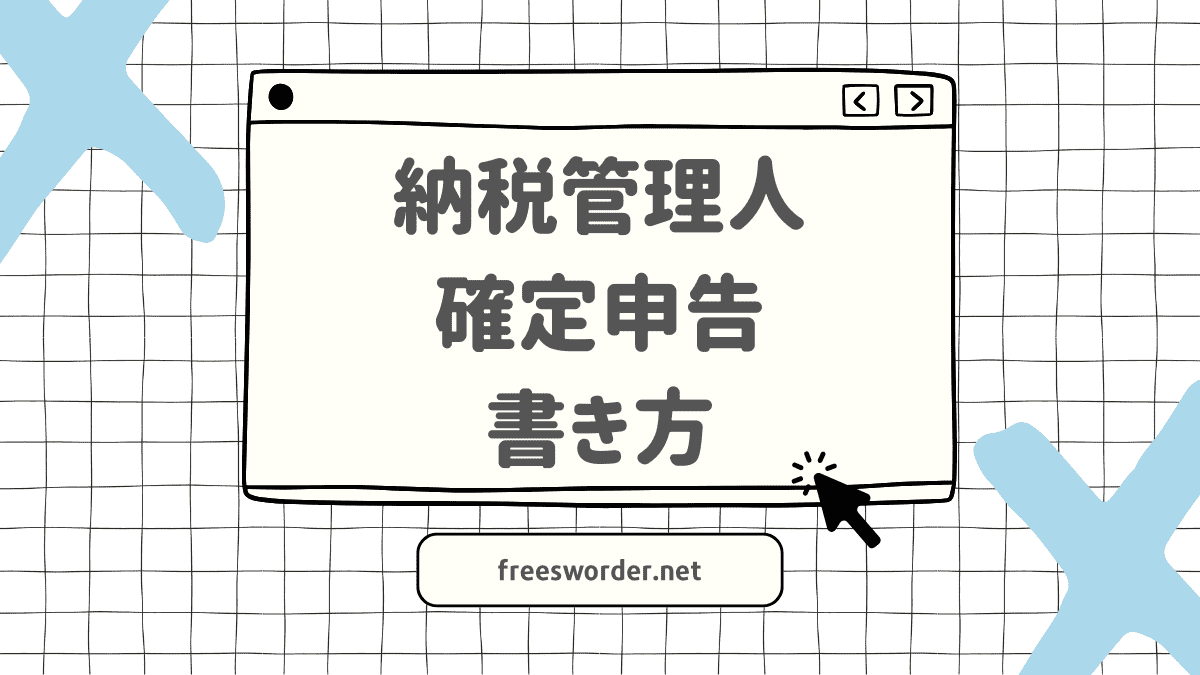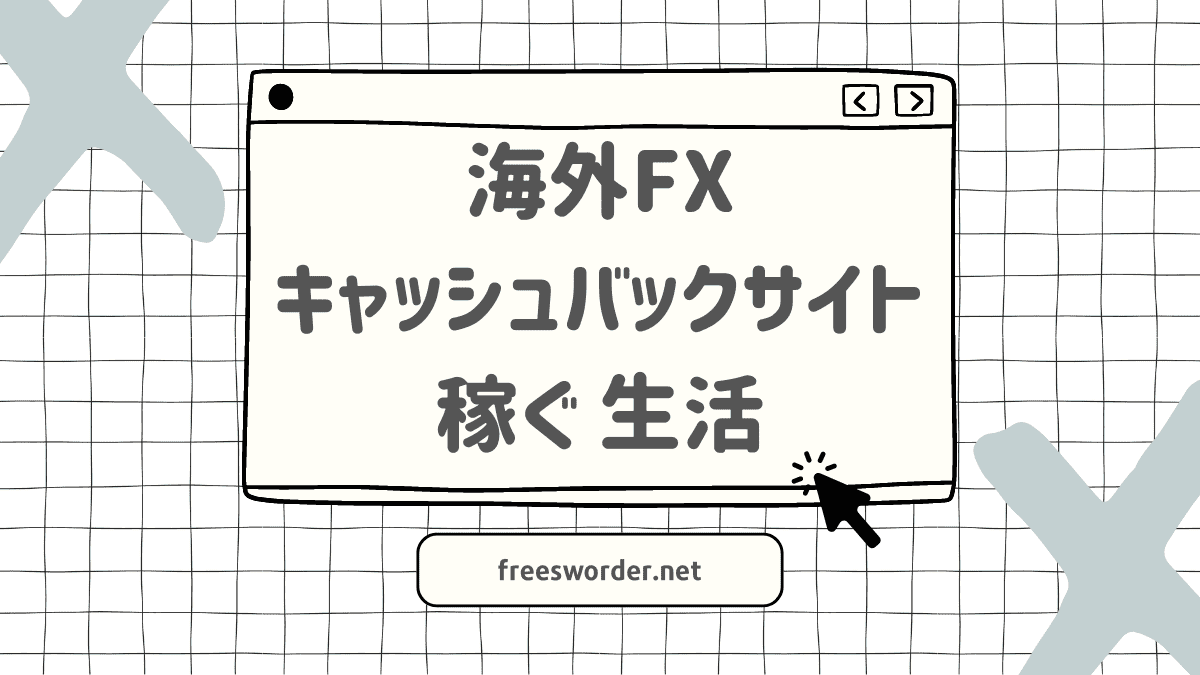海外在住者が日本の確定申告に取り組むとき、誰もが一度はつまづくポイントがあります。
それが、納税管理人を定めた場合の「書類の書き方」です。
どこに納税地を書く?
納税管理人の情報は?
海外の住所はどこに書く?
こんな疑問が次々にわいてきます。
でも、国税庁のマニュアルにはほとんど書かれていません。
実際に僕自身、海外から初めて確定申告をしたときに、何度も調べて、試して、ようやくたどり着いたのが今回の方法です。
この記事では、非居住者として納税管理人を立てた場合の確定申告書類の書き方を、ステップ形式で徹底解説していきます。
非居住者と納税管理人の基本を押さえよう
まずは基礎知識から整理しておきましょう。
非居住者とは?
「非居住者」とは、日本に1年以上住所も居所もないと判断された人のこと。
以下のような人は、非居住者になります。
- 海外転勤・駐在で長期滞在している
- ワーケーションやノマドで日本を離れている
- 国際結婚などで海外移住した
ポイント:出国してから1年以上日本に住んでいなければ、原則として非居住者扱いになります。
納税管理人って誰?
非居住者になると、日本に住所がないため、税務署とのやり取りが困難になります。
その代理人として指定するのが納税管理人(のうぜいかんりにん)です。
納税管理人が担うのは、以下のような役割です。
- 所得税の申告・納付
- 還付金の受取
- 税務署からの書類対応
非居住者の「手となり足となる存在」と言っても過言ではありません。
納税管理人に誰を選ぶべき?
納税管理人に指定できるのは、成年の日本在住者であれば基本的に誰でもOK。
| 候補者 | 指定可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 親・兄弟 | ○ | 印鑑と本人確認書類があればOK |
| 配偶者 | ○ | 手続きしやすくおすすめ |
| 税理士 | ○ | 有償だが安心感が高い |
| 友人・知人 | △ | 信頼関係が重要 |
| 未成年 | × | 法的に契約行為が難しいため不可 |
納税管理人を立てると何が変わる?
大きく変わるのは、確定申告書の「住所欄」「納税地」「提出先」です。
- 申告書には、納税管理人の情報を書く
- 納税地の税務署に提出する
- 自分のマイナンバーや印鑑は使わないケースが多い
納税管理人と税理士はどう違う?【役割と選び方】
非居住者の確定申告に出てくる「納税管理人」と「税理士」。
どちらも“代わりに申告してくれる人”のように思えますが、役割と立場はまったく異なります。
ここでは、2者の違いと、どう選ぶべきかをわかりやすく解説します。
① 納税管理人と税理士の役割の違い
| 項目 | 納税管理人 | 税理士 |
|---|---|---|
| 目的 | 税務署との連絡・書類提出の代行 | 税務申告の専門家として内容を作成・代理提出 |
| 誰がなれるか | 成年で日本在住なら誰でも(家族・知人OK) | 税理士資格を持つ専門職のみ |
| 報酬 | 無料〜実費程度(知人や家族) | 原則として有料 |
| 手続きに必要な書類 | 「納税管理人の届出書」が必要 | 委任状または税理士証票で対応可能 |
| 印鑑 | 管理人の印鑑を使用 | 税理士の職印または電子署名 |
結論:納税管理人=届け出さえすれば誰でもOK、税理士=税のプロフェッショナル
② どちらを選べばいい?【判断基準】
パターンA:節税対策までは不要 → 納税管理人で十分
- 会社員の副業や不動産収入など、シンプルな収入構成
- 自分で申告書を作って、提出だけ頼みたい
- 家族にお願いできる環境がある
→ この場合は納税管理人の方がコストも抑えられて◎
パターンB:節税や複雑な申告が必要 → 税理士に依頼すべき
- 事業所得や仮想通貨などで計算が複雑
- 海外との二重課税が気になる
- 確実に節税したい or 税務調査が怖い
→ 税理士は高額だが、その分“リスク回避力”が高いです。
③ 税理士が納税管理人を兼ねることも可能
実は、税理士に「納税管理人の届出書」も提出してもらえば、両方を兼任してもらうことができます。
- 申告書の作成と提出を一括対応
- 印鑑や提出先管理も全部任せられる
- 海外在住者向けに慣れた事務所も多い
費用はかかりますが、確実性を求めるならベストな選択肢です。
「誰に任せるか」は、確定申告のスムーズさを大きく左右します。
信頼性・費用・内容の複雑さをもとに、自分に合った方法を選びましょう。
この後の章で、実際の記入方法を1つずつ解説します。
書類作成前のチェックリスト7選
いきなり記入を始めるのではなく、まずは必要書類を揃えるのが成功のカギです。
以下のチェックリストを参考に、事前にしっかり準備しておきましょう。
書類準備リスト
| 番号 | 書類名 | 優先度 | 補足 |
|---|---|---|---|
| ① | 納税管理人の届出書 | ◎ | 税務署に事前提出しておく |
| ② | 確定申告書B(第一表・第二表) | ◎ | 国税庁サイトまたは会計ソフトで作成可能 |
| ③ | 所得の証明書 | ◎ | 源泉徴収票・収支内訳書など |
| ④ | 控除証明書 | ○ | 保険料控除・ふるさと納税など任意 |
| ⑤ | 納税管理人の現住所・印鑑 | ◎ | 押印に必要(本人印は使わない) |
| ⑥ | 海外の現住所メモ | ○ | 英文で正確に記載できるように |
| ⑦ | マイナンバー(未記入でもOK) | △ | 非居住者は未記入でよい |
ポイント:freeeなどの会計ソフトを使う場合も、印刷前に必ず内容確認を!
確定申告書B 第一表の書き方【記入項目ごとに解説】
ここでは、実際の申告書を見ながら「どこに何を書くか?」を具体的に説明していきます。
書類作成の要点は以下のとおりです。
① 納税地の記入方法
左上の「住所」欄には、納税地として指定した住所を記入します。
納税地=納税管理人の住所ではありません。
原則として、次のいずれかを記載します。
- 日本国内で過去に住んでいた住所
- 住民票を置いたままにしている実家
- 事業所(日本国内にある場合)
納税管理人が税理士で、住所を貸与している場合はその事務所でもOK。
② 税務署名の書き方
「税務署名」欄には、上記の納税地を所轄する税務署の名称を記入します。
- 例:新宿区なら「新宿税務署」
- 例:大阪市北区なら「北税務署」
調べ方:
国税庁の税務署検索ページで確認できます。
③ 納税管理人の住所・氏名の書き方
納税地と混同されないよう、納税管理人の情報には以下の記述ルールを設けましょう。
- 「納税管理人住所:〇〇県〇〇市…」のように明記する
- 納税管理人の氏名は「屋号欄」に記載する(freeeもこの運用)
④ 海外の現住所の書き方
申告書には、1月1日時点で居住していた海外住所を記入します。
記入例:
123/45 Nguyen Trai, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
- 英語表記が原則
- 都市名・区名・番地・国名の順で記載
- 郵便番号もあれば加えてOK
⑤ 氏名・フリガナ・職業・生年月日
- 氏名:戸籍通りのフルネームを記入
- フリガナ:カタカナで記入(忘れがちなので注意)
- 職業:開業届に記載したものと揃える(例:Webライター、翻訳業)
- 生年月日:和暦または西暦どちらでも可
⑥ 世帯主・属柄・電話番号
- 世帯主:通常は自分の名前を記入
- 属柄:「本人」と明記
- 電話番号:海外携帯の場合、国番号付きで記載(例:+84-90-XXXX-XXXX)
⑦ 印鑑は納税管理人のものを使用
非居住者本人は日本にいないため、印鑑欄には納税管理人の印を押します。
- シャチハタはNG
- 印鑑証明書は不要
- freeeで電子申告する場合は省略可能
第二表・第三表の書き方でつまずかないために
第一表を書き終えたら、次に進むのが第二表・第三表。
これらは所得の詳細や控除内容を記載するパートです。
納税管理人を定めた非居住者の場合でも、基本的な記入ルールは変わりませんが、いくつか注意点があります。
① 第二表での注意点
第二表では、次の内容を記載します。
- 所得の種類と内訳
- 配偶者・扶養親族の情報
- 控除の種類と証明書の有無
注意すべきポイントは以下のとおりです。
- 扶養控除や配偶者控除は、同居が前提の制度なので慎重に判断
- 国外に住む扶養親族は証明書類(送金証明・パスポートコピーなど)が必要
- 保険料控除・社会保険控除は、日本で支払っている場合のみ適用可
「使えそうな控除が全部使えるわけではない」点に要注意。
② 第三表での注意点(該当者のみ)
第三表は、以下のような所得がある人が対象です。
- 事業所得がある(個人事業主)
- 不動産所得がある(賃貸など)
- 株式の譲渡やFXの雑所得がある
非居住者でも、日本国内に不動産を所有していれば第三表の記入が必要です。
記入する代表項目:
- 所得の種類ごとの金額
- 必要経費の内訳(減価償却など)
- 青色申告の有無
事業所得や不動産所得がある方は、収支内訳書や青色決算書も別途提出が必要になります。
非居住者でも使える控除まとめ【知らないと損】
非居住者になっても、すべての控除が使えなくなるわけではありません。
むしろ、条件さえ満たせば居住者と同じように控除を活用できるケースもあります。
この章では、実際に使える控除・使えない控除を一覧で整理しつつ、申告時の注意点も解説します。
① 非居住者が使える主な所得控除
以下は、非居住者でも利用可能な控除の代表例です。
| 控除の種類 | 利用可否 | 説明・条件例 |
|---|---|---|
| 社会保険料控除 | ○ | 日本で国保・年金などを支払っている場合のみ |
| 生命保険料控除 | ○ | 支払先・保険契約者が本人なら対象(証明書必須) |
| 地震保険料控除 | ○ | 日本国内の物件が対象なら可 |
| 寄附金控除 | ○ | ふるさと納税など、日本国内の対象団体への寄附が条件 |
| 医療費控除 | △ | 日本国内での治療・支払いのみ対象(海外医療費は不可) |
| 雑損控除 | △ | 日本の資産に損害が発生した場合に限る |
ポイント:国内での支払い・資産・契約が前提。海外の支出は原則対象外です。
② 使えない(または適用が困難な)控除一覧
一方、以下の控除は非居住者には原則適用されません。
| 控除の種類 | 適用不可理由 |
|---|---|
| 基礎控除(48万円) | 非居住者は対象外と明記(所得税法) |
| 配偶者控除 | 同居条件あり。海外居住配偶者は対象外 |
| 扶養控除 | 海外扶養者を対象にするには送金証明など厳格な条件が必要 |
| 寡婦(寡夫)控除 | 国内に居住実績がないと申告が困難 |
補足:扶養控除は絶対NGではありませんが、国税庁も「原則不可」スタンスです。
③ 控除証明書の提出ルール
freeeや紙で申告する場合でも、以下のルールを守る必要があります。
- 保険料・地震保険などは原本かPDFの印刷版を添付
- 寄附金控除は自治体発行の受領証明書(寄附年月日・金額・団体名明記)が必要
- 医療費控除は医療費控除の明細書と領収書の保管がセット
非居住者でも、添付書類の要件は居住者と同じです。
④ 控除を使うと還付が大きくなる
特に「源泉徴収あり」の収入(例:不動産所得、配当所得)がある非居住者にとって、
控除を使うことで還付金が数万円〜十万円単位になるケースもあります。
控除を正しく使えば、税額は大きく変わります。
知らずに損する前に、しっかり確認しておきましょう。
freeeで納税管理人付き確定申告をする方法
freee(クラウド会計ソフト)は便利ですが、非居住者+納税管理人対応は少しクセがあります。
そのまま使うと間違った書類になることもあるため、手動編集がカギになります。
① 必ず「直接入力編集」モードに切り替える
freeeの確定申告書類作成画面では、納税管理人を前提にした入力欄がありません。
そのため、
- 通常どおり申告書を作成
- 最後の「書類提出」直前で
- 「直接入力編集」モードを選択する
この手順で進める必要があります。
ポイント:一度PDFを出力して、誤記がないか印刷前に確認を。
② カスタマイズすべき3つの項目
freeeで納税管理人対応をするには、以下の3点を手動編集する必要があります。
| 項目 | 編集内容例 |
|---|---|
| 納税地住所 | 過去に住んでいた実家や事業所の住所を入力 |
| 屋号欄 | 「納税管理人氏名」を記入(freeeの標準ルール) |
| マイナンバー欄 | 空欄にする(非居住者は失効扱い) |
この3項目を整えるだけでも、紙提出用としては十分に使えるレベルになります。
③ 提出時の注意点
freeeで作成したPDFを印刷する場合、
- 書類左上の「税務署名」欄に提出先を明記
- 印鑑欄には納税管理人の印を押す
- マイナンバーが空欄でも、非居住者であればOK
電子申告(e-Tax)は、非居住者には対応していないケースが多いため、「紙での郵送提出」が確実です。
freee以外のクラウド会計ソフト3選【非居住者向け】
確定申告書の作成にfreeeを使う方は多いですが、
「freeeは非居住者に完全対応していない」と感じる場面もあります。
そこでこの章では、非居住者でも使いやすい他の会計ソフト3つを紹介します。
それぞれに特徴があるので、自分のスキルや目的に合ったツール選びの参考にしてみてください。
① 弥生会計 オンライン(やよいの青色申告)
特徴:紙出力前提&シンプル設計で自由度が高い
- 非居住者・納税管理人欄などの直接入力が可能
- freeeよりクセが少なく、PDFの手直しがしやすい
- 電子申告が前提でないため、紙提出派におすすめ
注意点:仕訳入力は手動中心なので、初心者にはややハードルあり
非居住者にとって:自由度が高くカスタマイズ前提なら強い味方
② マネーフォワード クラウド確定申告
特徴:会計初心者にも優しいが、住所管理に制約あり
- 入力ナビがわかりやすく、フローに沿って進められる
- UIが直感的で初心者にも使いやすい
- ただし、非居住者住所の設定や納税管理人情報の記入が想定されていない
非居住者にとって:freee同様、直接入力による調整が必須。万人向けではない。
③ Taxnote(タックスノート)
特徴:スマホ入力+最小限の帳簿管理に特化
- 入力画面がシンプルで、出先からの記帳がラク
- 決算書は出力できるが、申告書の自動作成には非対応
- 本格的な確定申告は別ソフトか税理士との併用が前提
非居住者にとって:日々の記帳+PDF作成には使えるが、申告書提出まではfreeeや弥生が必要
補足:freeeの強みもある
freeeは「直接入力編集」で対応できるほか、青色決算書の自動作成など事業者向けの機能は圧倒的に充実しています。
ただし、非居住者にとっては「住所・屋号・マイナンバーなどを自力で直せる」リテラシーが求められるため、
「freeeありき」ではなく、自分に合った選択肢を持っておくことが大切です。
書類提出の方法と提出先を間違えないために
最後のステップが、確定申告書の提出方法です。
納税管理人を通じて出す場合でも、いくつかルールがあります。
① 提出先は「納税地を管轄する税務署」
ここが最大の注意点。
「納税管理人の住所を所轄する税務署」ではなく、あくまで「納税地の税務署」に提出します。
- 納税地=非居住者が指定した元の住所(または日本に残している事業所)
- 税務署検索はこちら(国税庁)
納税管理人が税理士であっても、税理士の管轄署に出すのは誤りです。
② 郵送で出すときのチェックリスト
郵送で提出する際は、以下を必ず同封しましょう。
- 申告書の原本(必要な枚数)
- 控えのコピー(返信用)
- 返信用封筒(宛名記入+切手貼付済み)
- 各種添付書類(収支内訳書、控除証明書など)
控えの返送が必要な方は、返信封筒を忘れずに。
③ 提出時期と締切
確定申告の提出期限は、毎年3月15日(休日なら翌平日)です。
ただし、還付申告であれば、翌年の1月1日から5年間提出可能です。
- 納税があるなら、締切厳守
- 還付だけなら、時間的余裕あり
納税管理人が期限内に提出してくれるよう、早めに動くのがベスト。
非居住者の確定申告でよくあるNG集【やりがちミス】
非居住者として初めて確定申告に取り組むとき、意外とやりがちなミスがあります。
中には、税務署からの問い合わせや再提出につながるものもあるため、
事前にチェックして未然に防ぐことが大切です。
ここでは、よくある失敗例とその回避法をセットで紹介します。
① 納税地に「納税管理人の住所」を書いてしまう
NG例:納税地=納税管理人の自宅住所にしてしまう
これは非常によくあるミスです。
納税地とは、非居住者本人が最後に住んでいた住所や、残している事業所の住所が原則です。
対策:
– 過去に住んでいた住所や不動産所在地を納税地に指定する
– 管轄税務署も納税地に基づいて決定する
② 屋号欄を空欄のままにして提出
freeeなどの会計ソフトでは「屋号欄」が自動で空欄になる場合があります。
この欄は、納税管理人の氏名を記載するために活用します。
対策:
– 「屋号=納税管理人の氏名」にする
– 印刷前にPDFを開いて、手入力でも補う
③ 印鑑欄に自分の印を押してしまう
非居住者本人が印鑑を押すと、現地(海外)での署名扱いになり、無効になる可能性があります。
印鑑欄は、納税管理人が押印するのが原則です。
対策:
– 管理人に申告書を郵送する際、「ここに押印」と明記する
– シャチハタ以外の認印でOK(印鑑証明は不要)
④ マイナンバーをうっかり記入してしまう
非居住者はマイナンバー制度の対象外になるため、記入は不要です。
それでも「欄があるから」と書いてしまう人がいますが、税務署で不要情報として扱われるだけです。
対策:
– マイナンバー欄は原則空欄で提出
– 添付台紙も不要(freeeでは非表示設定にできる)
⑤ 控え・返信封筒を同封せず、確認ができない
郵送提出時に控えの返送が届かない…というトラブルも頻発します。
対策:
– 提出書類のコピーを取り、必ず返信封筒を同封
– 封筒には自分の日本の実家など、届く住所を明記
これらのミスを避けるだけでも、トラブルの9割は防げます。
提出直前には、チェックリスト形式で再確認するのがおすすめです。
提出から還付までのタイムスケジュール【実例ベース】
非居住者が納税管理人を通じて確定申告をした場合、どのくらいの期間で処理が完了するのか?
気になる方も多いと思います。
この章では、実際のスケジュール感をベースに、提出から還付までの流れを整理しておきます。
① 申告書の作成から提出までの工程
一般的なスケジュールは次のとおりです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ステップ① | 1月下旬〜2月上旬:freeeなどで確定申告書を作成 |
| ステップ② | 書類をPDFで保存・印刷し、納税管理人へ郵送 |
| ステップ③ | 納税管理人が税務署に申告書を提出(持参または郵送) |
ポイント:2月中旬までに書類を完成・提出できると理想的です。
② 提出後〜還付金の入金までの目安
税務署での処理には時間がかかる場合があります。
還付申告の場合のスケジュール目安は以下のとおり。
| 日程 | 目安となる処理 |
|---|---|
| 提出後 1〜2週間 | 書類が税務署に届き、順次処理がスタート |
| 提出後 約3週間 | 還付金の振込処理が完了し、納税管理人の口座へ入金 |
| 提出後 約1か月 | 還付通知が管理人へ到着、自身へ送金・通知してもらう |
全体として、提出から約3〜5週間が目安になります。
③ スケジュールを組むときの注意点
- 納税管理人と事前にスケジュールを共有しておくこと
- 控え返送や添付書類の不足があると、処理が止まる
- freeeの出力PDFは余裕を持って管理人へ渡す
早めに動くほどトラブルを回避でき、結果的に還付も早くなります。
よくある質問(FAQ)
ここでは、納税管理人を定めた非居住者の確定申告について、よくある質問とその答えをまとめておきます。
| 質問内容 | 回答 |
|---|---|
| 納税管理人は税理士でないとダメですか? | いいえ、家族や知人でもOK。信頼できる成年であれば問題なし |
| 海外の収入は日本で申告する必要がありますか? | 原則不要。ただし日本国内源泉所得があれば申告が必要です |
| マイナンバーは書かなくてよいですか? | 非居住者であれば記入は不要(空欄でOK) |
| 提出先の税務署は納税管理人の住所で決める? | いいえ、あくまで納税地(日本の旧住所など)で判断します |
| e-Taxで申告できますか? | 非居住者はe-Tax不可(日本の住所が前提のため) |
| freeeは納税管理人対応していますか? | 公式対応ではないが、「直接入力編集」で対応可能です |
補足:クラウド会計ソフトは万能ではありません。紙提出前提で確認しましょう。
まとめ:非居住者の確定申告は段取りがすべて
最後に、今回の記事のポイントを3つにまとめます。
① 納税管理人がいれば非居住者でも申告できる
- 日本国内で所得があるなら、非居住者でも申告義務あり
- 納税管理人は家族・知人でもOK。事前に届出を出すこと
- 申告書には、納税地・納税管理人・海外住所のすべてを正しく書く
② freeeや紙ベースで柔軟に対応しよう
- freeeであれば「直接入力編集」で管理人対応の申告書が作れる
- 屋号欄・住所欄・マイナンバー欄を手動でカスタマイズ
- 提出は「税務署への紙提出」が最も確実でおすすめ
③ 期限とスケジュール管理が成功のカギ
- 納税地に応じた税務署へ、納税管理人経由で提出
- 還付目的の人も、5年以内に出せばOKだが早めの対応が安心
- 控えや添付書類の忘れがないよう、封筒にはチェックリストを同封
納税管理人制度を使いこなせば、海外生活中でも日本での納税がスムーズに。
この記事が、これから確定申告に取り組む非居住者の一助になれば幸いです。